※この文章は、暗号解読をするかJavaScriptを解除して、コピーを図った場合に表示されます。
このページは、小説の無断転写や二次加工を防ぐために、マウスコマンド制御やソースの暗号化などを設定しています。というのも、管理人は小説をweb公開しておりますが、著作権の放棄はしておらず、パクられるのがイヤだからです。サイト主旨をご理解の上、小説は当サイト内でのみお楽しみくださるようお願い致します。
いかにして天より隕(おち)しや。
諸々の国をたふしし者よ。
いかにして斫(きら)れて地にたふれしや。
(『旧約聖書』イザヤ書14章12節より)
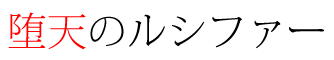
エイトは世界地図をテーブルに広げながら、今まで見たことのなかった世界の形を眺めている。目線は地図上を漂っているが、先程からずっと己に注がれている視線にもどかしい思いをさせていた。
「視線を感じるんですけど」
「熱いやつをな」
「……」
伏せた瞼はそのままに、彼が瞳だけを動かしてその方向を見つめると、凄艶の眼差しを降り注いでいたククールと瞳が合う。
彼はベッド脇のサイドテーブルに肘をついて、その細い顎を乗せてこちらを眺めていた。
「可愛いなと思ってさ」
手の甲に乗せた華顔はやや傾き、上目遣いでその美しい瞳を向ける姿は男にしては艶っぽい。長い銀の睫毛の奥から覗く淡いブルーが、やや挑発的な色を乗せてエイトを縫いとめている。
「なっ、」
彼に子供のようにあしらわれるのは初めてではない。
これでもトロデーン城では一人前の近衛兵士として仕えていたエイトである。可愛いと言われて喜ぶ性別でもなければ、それ程若い年齢でもない。エイトは毎度の事ながら彼に揶揄われたような気になって、地図に落としていた顔を上げてククールを睨んだ。
「世界を初めて知ったって顔してるぜ」
「っ、」
しかし言われた言葉は図星で、エイトはマルチェロより渡された羊皮紙の包みを解いた時、それが何だか一瞬では分からなかったくらいである。マイエラ修道院に何点かあるという世界地図のひとつを旅の用立てにと貰った訳だが、地図が旅人の必携品であるといえども、全世界を網羅したそれを手に入れることは難しかった。その貴重さは勿論の事、エイトは初めて見る世界の大きさに驚き、旅程を考える時以外でもこれを広げて眺めることが多かった。
一方、僧侶という職業上、世界の各地に巡礼と祈りを唱えに行くククールにとっては見慣れたもので、彼には地図を広げて好奇の瞳を輝かせるエイトの方が面白かったりする。
そう、エイトは暇さえあればそれを眺めているくらいで。
「お前がそういう瞳して地図見てるのを可愛いと思う反面、嫉妬してたりして」
ようやく己の注ぐ視線に反応を示したエイトに麗しい微笑を見せながら、彼は少々の苦笑を織り交ぜて詰ってきた。
口角を軽く持ち上げて薄く笑う、蠱惑的な表情。彼と瞳を合わせたエイトは、その誘うような甘いマスクに頬を染めながら、心中で改めて彼が美形だと思う。
「、」
そんな彼に射止められ、軽く詰られた自分は何と返せば良いのか。
言葉を失い戸惑っていたエイトは、瞳を繋いだままこちらに近付いてくるククールに躊躇した。多分、その緊張は彼にも十分伝わっているのだろう。ククールはやや身体を硬直させて己の接近に警戒するエイトを半ば愉しむように見ていた。
「やっぱ可愛い」
「っ、」
その無知故の好奇心が醜い嗜虐心を擽る。
世界の大きさを知らぬ彼は、恐らく人の深さも左程知らぬのだろう。無垢のままに輝く瞳は距離を縮めたところで漸く逡巡の色を見せたが、その微動にさえ自分は擽られて。
「キスしても良い?」
ククールはゆっくりとエイトの頬に触れると、なぞるように顎のラインを辿って口元へと指を運んだ。
「ックク、」
いつもは断りなく、そして所構わず唇を奪っていく彼が、改めてこのように尋ねてくるとは。
その長い人差し指に顎を持ち上げられたエイトは、妖艶な眼差しで許しを乞うてくる彼の様子にただならぬ警戒心を抱いてしまう。
「ッ、駄目」
驚きに薄く開いていた唇は、不意に言葉を漏らして彼を拒んでいた。
「イヤ?」
その低音はやけにエイトの胸をさざめかせる。擽られるような感覚に陥ったエイトは、接近する彼から逃げるよう背を反らせて構えた。
「やっぱり受け入れられない? あの日の夜は衝動だったとか?」
ククールは彼より高い身長を屈め、たじろぐエイトの瞳を上目に覗き込んだ。
「それとも同情で俺に抱かれた?」
純粋無垢の穢れない瞳に映った己の姿を見る。
ククールが天使のような彼を堕としたのはつい先日。甘い言葉を紡ぎ、淫らな愛撫で昂ぶるエイトの肉体を味わって、その白い羽を引き千切って貪った。童貞の彼が瞳を不安と怯えに震わせながらも、次第に解き放たれる快楽に飲まれて嬌声を挙げ、昂ぶる肉体に猛る欲望を迎え入れた姿はまだ鮮明に思い出せる。ククールの白い肌には未だ彼の爪痕や歯型が赤く浮き立っており、そしてエイトの柔肌にはククールの吸い跡が点々と残っていた。
それはいつかの夜の強欲の証。
「………………」
聞いたエイトは彼に刻まれた情欲の記憶を呼び起こすと、不覚にも頬を朱に染め上げたが、同時にククールの自嘲を含んだ物言いに耳を反応させる。
先の夜を一時の過ちだったという彼にエイトは首を振った。
「違う」
衝動でも同情でもない。
まさか彼の口からそのような自虐的な言葉が吐かれるとは思ってなかったエイトは、普段は穏やかな表情に真剣な怒りを乗せて続ける。
「ククが思ってるほど僕は優しくない」
エイトはククールを受け入れたあの晩、言わねばならぬと思っていながら口に出せなかった事を言った。
彼は自身を悲観的に追い込むきらいがある。それは彼が由緒正しき伝統を誇る格調高き聖堂騎士団にあって、その破天荒かつ反抗的な性格故に僧侶として馴染めなかった所為か、またはその逆、彼こそが最も神を純粋に愛していたからこそ苛んだ所為か。しかしエイトには、ククール自身が複雑な感情に戸惑っているのだということだけは明らかだと思った。
兎角ククールは自分を清純な人格に創り上げる。エイトはそれが自分を揶揄う為というより、彼自身の心の闇に起因するのではないかと思っていた。
「僕は君を救おうと身体を差し出すほどお人好しじゃないし、」
迫るククールを拒まなかったのは慈悲でも慈愛でもない。
「君の為に嘘を吐けるほど器用な人間でもないよ」
あの夜に囁いた言葉と差し出した身体に偽りはない。
ククールの抱擁と愛撫を「嫌じゃない」と零し、彼の全てを迎え入れた最後には「良い」という言葉にまで変わっていたエイト。今思えば刹那に過ぎ去った恍惚の中で、自分は心のままに感情を吐き出し、彼に劣情を晒していた。
しかしククールの方はまだそんな自分を清らかな慈善での行為だと、己の本心に反する許容だと思っているとは。エイトはややその真剣に怒気を含ませて、普段はなかなか外面には出てこない感情が伝わるようククールの瞳を見つめる。
「………………」
「エイト」
エイトがこのような表情を見せたことはこれまでにあっただろうか。
ククールは鋭い視線も可愛らしいと内心で見惚れたが、その瞳の奥に見える彼の本気を感じ取ると、魅了されている場合ではないと改める。
「………………」
あの夢のような一夜。エイトは全ての情欲を解き放って達した瞬間、甘美な嬌声の中で「好き」だと言って抱かれる腕にしがみついていた。ククールがもう一度その言葉を確かめようと彼の脱力した身体を胸元に引き寄せた時、エイトの紅く熟れた唇は甘美な吐息を漏らすのみだった。
ククールは彼が初めて人前で達した恥ずかしさに何も言えなくなっていたのかと思っていたが、あの時の彼は心内を晒すことに照れていたというのか。
「僕はククみたいに感情をそのまま出すのが苦手だから、」
彼の心の問いには、目の前の本人から答えが返される。
「突然キスされるのも、好きって言われるのも、それに今みたいに改まってキスしていいかって聞かれるのも、イヤじゃないけど、……恥ずかしい」
それがエイトの本心だった。
「………………」
聞いたククールは、エイトが感情を示す言葉を言ったことにやや驚く。
辛うじてイエスとノーを首で表す程度の彼が、あの官能の波間でならまだしも、素面で「恥ずかしい」と言ってくれるとは思ってもみなかった。もしかエイトは、どんな強敵に向かうより大きな勇気を出しているのではないかと思う程で、ククールは何故だか情事の時以上に彼を追い詰めているような気分になってしまう。
「ごめんな、エイト。ちょっと揶揄い過ぎた」
あまり恋人を虐め過ぎるのは趣味じゃないと、ククールは長い銀糸の髪を掻いて苦笑した。
「俺ってエイトが思ってるほど意地悪じゃねぇから」
なるべく彼の警戒心を掻きたてぬよう言ってやる。
「お前のイヤがる事はしたくない」
羞恥心に染まる相手に嗜虐性を煽られるのは男の性だとしても、強引に持ち込むまで堕ちてはいない。ククールはエイトが拒否を示すなら、互いが深く傷つかぬうちに手を引く理性を持ち合わせていた。蓋しそれは痛みに慣れた彼らしい思考。
「だから聞いたんだぜ? キスしていいかって」
しかし自重してみせた所で彼の色気が削がれることは余程なく、反応を窺って注がれる上目はエイトを誘うよう。
「結局は僕を揶揄ってるんでしょ」
エイトは参ったとばかり軽い溜息を吐くと、構えていた身体の緊張を解いて彼と向き合った。
「いいよ、」
これは彼なりの反抗なのか挑戦なのか。
エイトは地図を広げたテーブルに浅く腰掛けると、ゆっくりと瞳を閉じて顎を持ち上げる。いつかの夜に堪能した瑞々しい唇が、今ククールの目の前に易々と差し出された。
「エイト」
なんという状況。二度とは手に入らぬと思っていた彼が再びキスを受け容れるとは。瞳を閉じて振り落とされる唇を待つ姿は彼の積極性を見るようで胸を擽られ、ククールは暫し閉口して魅入ってしまう。
「早くしてよ」
エイトは黒い睫毛を恥じらいに震わせながら急かした。やはり今の状態は彼にとって羞恥心に染められるらしく、頬を紅潮させながら詰る姿は愛らしい。
そして何よりキスを待つ唇は更に煽情的だった。
「なんか、」
ククールはエイトの瞼にかかる前髪をそっと取り払って呟く。
「目ェ瞑って待ってるお前、凄え可愛いからさ、」
柔らかい黒髪はサラサラと横へ寄せられ、彼の凛々しい柳眉や長い睫毛を露にした。
エイトは閉じた瞳に視覚を奪われながらも、ククールの長い指が己の目元や額を撫でていく様子を敏感に感じる。唇が塞がれてしまえばこのようなもどかしい思いをしなくて済むのに、と思ったその時、エイトに真向かうククールから悪戯な口調が耳に届いた。
「キス以上の事、したくなっちまった」
「っ、」
エイトが身を預けたテーブルに、ククールが彼を覆うよう両手をかけたのが判る。この微細な振動と言葉に驚いたエイトは、溜まらず身構えて瞳を開いた。
「だっ、だめだめだめだめ!」
「イヤなのか?」
そうエイトが抵抗する間にも、ククールは彼の肉体をテーブルに押し倒して被さってくる。
「恥ずかし過ぎて、死んじゃいそうだよ!」
まさかテーブルの上でなんて。
エイトは眺めていた地図が己の肉体によって敷かれ、羊皮紙が乾いた音を立てて皺寄るのを背中で察知すると大いに慌てた。勿論、地図の心配をしている身ではないという己の状況には尚更動揺を隠せない。
エイトの焦りを見たククールは、「死ぬ」という彼の言葉に反応して綺麗に笑って見せる。
「大丈夫。そん時は俺が蘇生させてやるから」
その微笑は酷く妖艶で見る者全ての胸をさざめかせて。彼の端整な瞳が伏しがちに己に注いでくるのを見たエイトは、その美しさに言葉を失った。
「気持ち良ーく、昇天していいぜ」
だからエイト、俺と堕ちろ。
許しを乞うてはいたが、結局は有無を言わせぬ押しの強さ。凄艶の佳人は息を飲むほど見事な微笑みを降り注いで、固いテーブルの上の恋人にそっと覆い被さっていった。
光を抱へ掲げし者、明けの明星ルシフェルよ
なんぢ如何にして天より隕(おち)しや
なんぢ如何にして天より隕(おち)しや
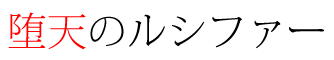
誠に主より愛され、その右の座に侍るを許されし唯一の者よ
なんぢ如何にして御意(みこころ)に叛き罪に穢れしや
なんぢ如何にして御意(みこころ)に叛き罪に穢れしや
エイトはククが思っているほどイイ子じゃないし、
ククはエイトが思っているほど悪い子じゃない。
そんな感じでラブラブしてればいいなぁ、という妄想。